
こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

イテテテ…。

あれ!ヒトケアさん、何か痛そうですね。

実は鼠径ヘルニアになってしまい、入院、手術が必要になりました。

えっ!それは大変ですね…。ケアマネ業務も心配ですね。
「もし、自分が病気やケガで動けなくなったら…」
ケアマネとして日々の業務を行いながら、そんな不安が頭をよぎることはありませんか?
特に、一人で事業所を運営している“一人ケアマネ”にとっては、自分の入院がそのまま業務全体の停止につながるリスクをはらんでいます。
そこで今回は、私自身の入院・手術の体験をもとに、入院中でもケアマネ業務を継続するための備えと工夫についてご紹介します。
- 一人ケアマネが入院する場合の業務継続に必要な準備とは?
- 入院中でも対応できる具体的なICT活用の実例
- 非常時に備えた“実効性のあるBCP”を作るためのヒント
いざという時にも慌てないためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。
1.入院前

鼠径部の違和感から受診へ
私はランニングが趣味で、毎朝5kmを走るのが日課でした。
さらに、妻が2025年3月の東京マラソンに出場予定だったこともあり、週末には14〜20kmの長距離練習にも付き添っていました。
その結果、月間の走行距離はさらに増えていきました。
そんな中、2025年2月23日(日)に20kmのランニングを行った後、左の鼠径部に違和感を覚えるようになり、次第に「ぽっこり」とした膨らみが現れてきました。
数日経ってもその違和感と膨らみは引かず、

もしかして鼠径ヘルニアかもしれない…
と思い、近所の診療所を受診することに。
その診療所でのCT検査の結果、「左の鼠径ヘルニア」との診断を受けました。
急を要する状況ではなかったものの、鼠径ヘルニアの根本的な治療には手術しかありません。
そのため、紹介状を受け取り、自宅近くの総合病院を受診しました。
総合病院での初診日に血液検査・レントゲン・心電図などの術前検査が実施され、「入院と手術に向けた準備」が本格的に始まったのです。
入院期間は月の下旬で設定
術前検査を終えた後、改めて病院を受診し、具体的な入院日を決めることになりました。
このとき私が最も意識したのは、「いかに業務への影響を最小限に抑えるか」という点です。
ケアマネの1ヶ月の業務は、おおまかに分けると以下のような流れになります。
- 上旬:前月実績の入力、国保連への請求
- 中旬:モニタリング訪問
- 下旬:サービス提供票の交付、要介護認定の更新に伴うサービス担当者会議
このうち、上旬・中旬の業務をあらかじめ済ませておくことで、業務のピークを避けた状態で入院できると考えました。
そこで、入院期間は4月23日(火)〜26日(土)の3泊4日に決定しました。
また、退院日を土曜日に設定したのには、次の2つの理由があります。
- 平日の業務への支障を少しでも減らせる
- 自宅に戻ってから週末を療養に充てられる
結果として、入院前日にはすべてのモニタリング訪問を終えた状態となり、安心して入院日を迎えることができました。
入院前日の準備
入院前日は、生活面と業務面の両方の準備を行いました。
1. 生活面の準備

- 衣類(パジャマ、下着、靴下など)
- 洗面用具(歯ブラシ、タオル、シャンプーなど)
- 消耗品(ティッシュなど)
- お菓子(小腹が空いたとき用)
2. 業務面の準備
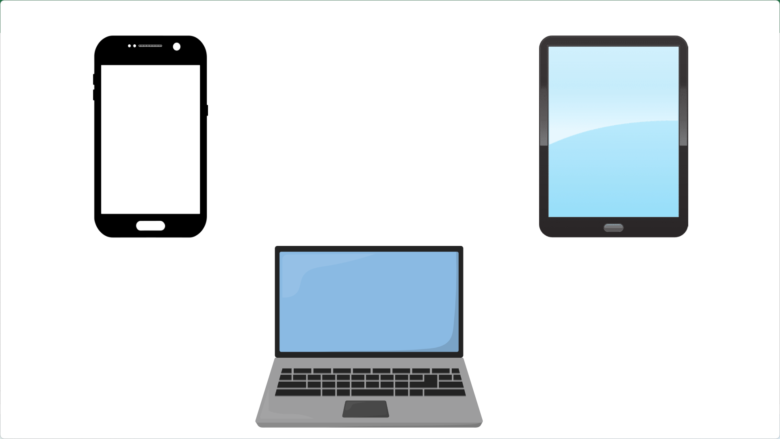
- ノートパソコン
- タブレット
- スマートフォン
これらの端末に加え、日頃から活用している以下のクラウドサービスや業務ツールを使える状態にしておくことで、病院内でも通常業務に近い形で対応できる準備が整っていました。
- クラウド型介護ソフト:カイポケ
- クラウドストレージ:Dropbox
- インターネットFAX:MOVFAX
- チャットツール:MCS、LINE WORKS、Chatwork
- メール:Gmail
- スケジュール管理:Googleカレンダー
- タスク管理:Google ToDo リスト
- IP電話アプリ:SUBLINE
これらのツールはすべて、スマートフォンやPCからのアクセスが可能です。
事務所にいなくても、日常業務の大半を対応できる体制を日頃から整えていたことが、今回の入院中に大いに役立ちました。
2.入院初日

入院当日のスケジュールと生活環境の確認
いよいよ入院当日。
事前に案内されていた時間に病院へ到着し、まずは入院受付を済ませました。
その後、入退院支援室で今後の流れや入院中の注意点などについて案内を受けました。

案内をしてくれたのは、担当利用者さんの入院時に連携している入退院支援看護師さんでした(笑)。
次に病棟へ移動し、担当の看護師さんから病室での生活ルールや設備の使い方、食事や検温の時間帯等の説明がありました。
また、
「手術前日の22時以降は絶食」
「アルジネードウォーターを就寝前までに2本、翌朝6時までにさらに2本飲む」
といった指示を受け、術前の準備が始まったことを実感します。
午後には麻酔科の医師と面談があり、翌日の手術で実施される全身麻酔について詳しい説明を受けたうえで同意書に署名。
この時点で、

いよいよ明日手術なんだ
と気持ちが引き締まりました。
デイルームを活用した業務継続の工夫
入院初日は手術前日ということもあり、体調面は元気そのもの。
病室で横になっているだけでは時間を持て余してしまうため、デイルーム(談話室)にノートパソコンを持ち込み、通常通り業務を行うことにしました。
病院にはWi-Fi環境が整っていましたが、安定性を優先してスマホのテザリング機能を使い、PCをインターネットに接続しました。
いつも通り、カイポケやDropbox、MCS、Gmailなどのツールを使用しながら、支障なく業務を進めることができました。
また、MCSを通じた多職種連携が自律的に機能していたおかげで、私自身が積極的に介入せずとも連携が取れていたことも心強いポイントでした。
あらためて、日常的にICTツールを活用しておくことが、いざという時の安心材料になると実感しました。
3.入院2日目

午前に手術室へ
入院2日目はいよいよ手術当日です。
とはいえ特に緊張することもなく、朝からデイルームにノートパソコンを持ち込み、いつも通り軽い業務をこなしていました。
午前10時前、病室に戻っていたところで看護師さんがやってきて、「手術時間が予定より少し早まりました」と一声。
この時点でようやく「いよいよか」と実感が湧いてきました。
指示に従って手術着に着替え、歩いて出術室へと移動。
手術室に到着すると、映画やドラマでよく見るような光景が目の前に広がり、どこか現実味のない感覚に包まれました。
室内では、担当医や麻酔科医、看護師の方々から改めて説明があり、最終確認を経て点滴から麻酔薬が投与されます。
「すぐに眠くなりますよ」と声をかけられた直後、まぶたが自然と落ちるように閉じ、意識はすーっと遠のいていきました。
術後の体調
気がつくと、人生初の手術は終わっていました。
麻酔から目覚めた直後はまだ朦朧としており、景色はぼんやりと見えていたものの、意識はまだはっきりせず、まるで夢の中にいるような感覚でした。
先生から「手術は無事に終わりましたよ」と声をかけられた記憶はありますが、手術台からベッドへ移乗された後は、そのまま再び眠りに落ちてしまいました。
次に目を覚ましたときには、病室のベッドで点滴とフットポンプが装着された状態。
術後6時間は安静が必要とのことで、起き上がることもできず、排尿も尿瓶を使用するよう指示されていました。
しかし、どうしても尿瓶での排尿に抵抗があり、トイレに行けるまで我慢することに。
そして22時頃、看護師さんに付き添ってもらいながら、なんとか歩いてトイレまで移動しました。
サイドレールに手をかけながら慎重に立ち上がったものの、傷口の痛みからスムーズに歩けず、トイレまでの距離が遠く感じました。
さらにベッドに戻った途端、激しい吐き気に襲われ、しばらくは身動きも取れないほどの状態に。

このとき、「手術って、やっぱり体にとって大きな負担になるんだ…」と痛感しました。
術後の業務継続
術後は6時間は点滴、フットポンプをつけた状態での安静が指示されており、ベッド上で過ごしていました。
全身麻酔の影響で吐き気が強く、スマホの文字を見るのも辛かったため、この日は無理に業務を進めず、極力最低限の対応にとどめることにしました。
それでも、家族や関係事業所からの連絡は発生します。
その際には、枕元に置いたスマホを使って、MCSやGmailでメッセージを確認・返信し、必要な連携は取るようにしました。
入院中でも「業務を止めないこと」は意識していましたが、それは決して「すべてをこなすこと」ではなく、体調と相談しながら、対応可能な範囲で行うものだと、身をもって学んだ一日となりました。
4.入院3日目
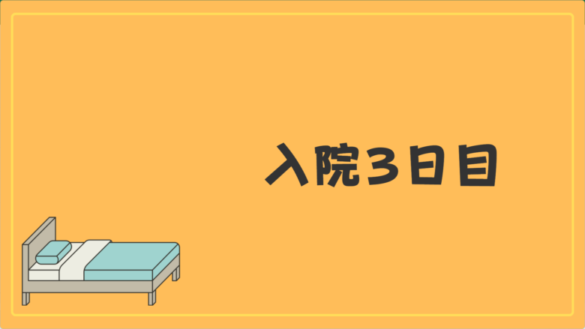
術後2日目の体調
一夜明けて、迎えた手術翌日の朝。
前日までの激しい吐き気はかなり落ち着き、ようやく頭がはっきりしてきました。
とはいえ、傷口の痛みはまだ強く、前日同様にサイドレールに手をかけながら、なんとか起き上がるという状態です。
朝食から食事も再開となり、久しぶりの固形物を口にして少しずつ元気を取り戻していきました。
午前中には点滴も終了し、以後の痛み止めと抗生剤は内服で対応。
この日は3日ぶりにシャワーを浴びることができ、身体がさっぱりすると同時に、気分もぐっと前向きになりました。
サービス提供票はベッド上から送信
術後2日目となるこの日は、体調が少しずつ回復してきたこともあり、ベッド上から業務を再開することにしました。
この日は4月25日で、翌月分のサービス提供票をサービス事業所へ交付する時期になります。
そこで、スマートフォンから「カイポケケア連携」を利用して、午前中のうちに一斉送信を行いました。
以前は、サービス提供票を印刷してファックス送信するまでに半日近くかかるのが当たり前でした。
それが今では、全事業所分の送信がわずか10分程度で完了します。
ベッド上にいながらでも、画面操作ひとつでサービス提供票の交付が完了するというのは、まさにクラウド活用の恩恵そのものです。
午後からリハビリを兼ねてデイルームへ
午後には点滴も外れて動きやすくなったことから、リハビリを兼ねてデイルームへ向かうことにしました。
まだ傷の痛みはありましたが、ゆっくりと歩いて椅子に座っただけで、

ここから元の生活に戻していくぞ!
という前向きな気持ちがふっと湧いてきました。
とはいえ、まだ本調子ではないため、疲れを感じたらすぐに病室に戻って横になることを意識し、無理はしないよう心がけました。
夕食後もデイルームで短時間だけ過ごし、早めに切り上げて就寝。
まだ本調子とは言えませんが、少しずつ普段の生活リズムを取り戻し始めた1日となりました。
5.退院日

午前に自宅退院
術後の経過も順調で、予定通りこの日の午前中に退院となりました。
荷物をまとめていると、清掃スタッフの方が、
「今日退院なんですね。おめでとうございます」
と笑顔で声をかけてくださり、弱っていた心身に、じんわりと沁みる温かさを感じました。
帰りは電動自転車に乗って、ゆっくりと自宅へ。
ほんの数日前までは手術台の上にいたとは思えないほどですが、体力はまだ本調子ではなく、

まずはしっかり休むことが仕事復帰の第一歩
と自分に言い聞かせながら帰路につきました。
週末は療養に
退院日は土曜日だったため、そのまま週末は無理をせず、療養に専念することができました。
翌日の日曜日は、入院前まで毎日走っていた近所の土手を、ペースを落としてゆっくりと散歩。
ランニングの再開にはまだ時間がかかりそうですが、それまでは散歩を日課にしていきます。
6.おわりに:BCP対策にはICTツールの活用が不可欠
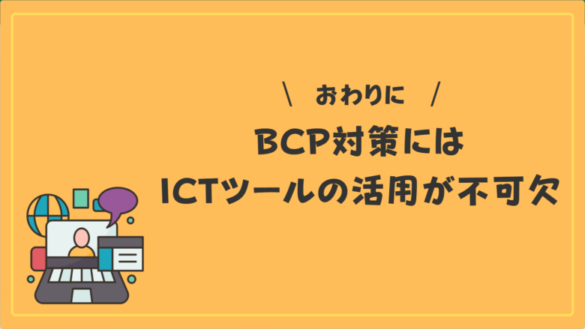
今回、鼠径ヘルニアによる入院・手術という非常時を経験したことで、業務継続におけるICTツール活用の重要性を実感しました。
特に、一人ケアマネにとって「自分が動けない状況」こそ、業務停止のリスクが最も高まる場面です。
そんな中でも業務を止めずに対応できたのは、日頃から以下のようなICT環境を整えていたからです。
- クラウド型介護ソフトの活用で、どこからでもケアプランの作成・管理が可能
- グループチャットにより、自分が介入しなくても多職種が自律的に連携できる
- クラウドストレージにより、どのデバイスからもファイルの保存・編集・共有がスムーズに行える
- IP電話アプリで、どこからでも事業所の代表番号に対応可能
- インターネットFAXにより、PCやスマホ上でFAXの送受信が完結
こうした仕組みが整っていたことで、場所にとらわれずに業務継続することが可能になりました。
ICTツールと聞くと、
「難しそう」
「自分には無理かも」
と感じる方もいるかもしれません。
ですが、少しずつでも使えるツールを取り入れていくだけで、働き方の自由度や非常時における業務の継続性は確実に高まります。

「いざという時」に慌てないためにも、まずはメールなどの身近なツールから業務に活用してきましょう。




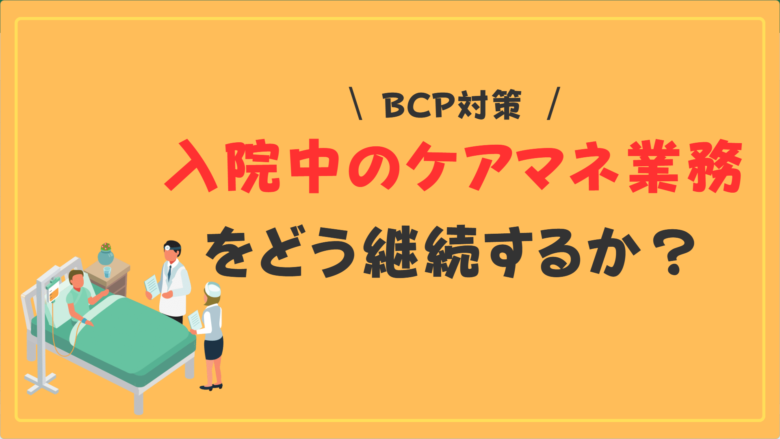


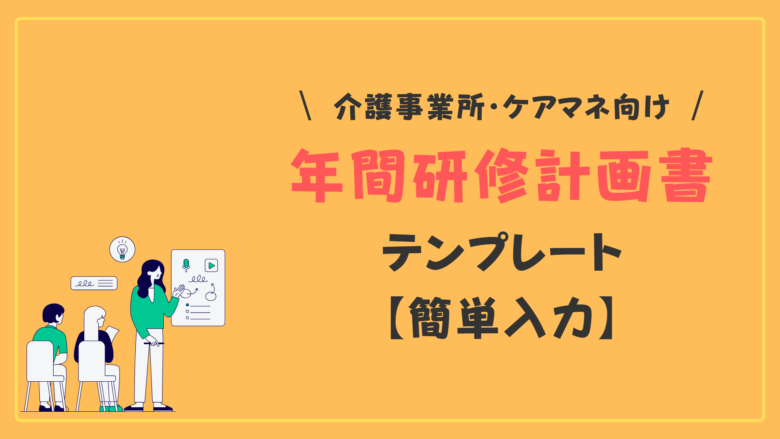
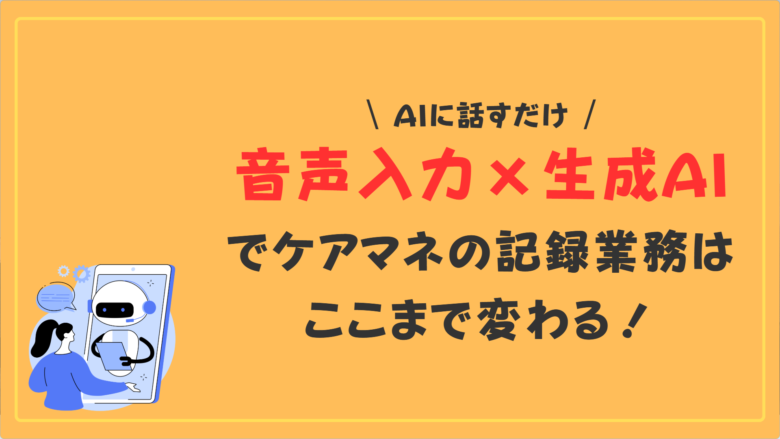
コメント