
こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

介護事業所にチャットツールでの連携を提案したところ『個人情報の心配があるので…』と断られてしまいました。
チャットツールを含む様々なICTツールは、多職種連携の強化や業務効率化を促進するための有効な手段となります。
一方、多くの介護事業所では現在も電話やFAXなどを連絡手段としており、新しいツールへの移行に対して慎重な姿勢を示します。
その理由としては、
「デジタルツールを利用することで個人情報が漏洩しないだろうか…」
といった漠然とした不安感が大きいのではないでしょうか?
この不安感は、
- 個人情報の漏洩リスク
- 不正アクセスの危険性
- 法的なコンプライアンスの問題
など、多岐にわたるリスクに起因しています。

ここで重要になるのが情報セキュリティです。

すみません、情報セキュリティって何ですか?
情報セキュリティとは、個人情報や機密情報などを保護し、不正なアクセスや漏洩、改ざんなどから守るための対策のことを指します。

情報セキュリティによって保護するのは、企業や組織などで保有している情報全般(情報資産)です。
今回の記事では、ケアマネ・介護事業所の皆さんに向けて、情報セキュリティの基礎知識と対策についてわかりやすく解説します。
安心安全にICTツールを活用したい方は今回の記事を最後までご覧ください。
ケアマネ業務に活用できるICTツールについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
情報セキュリティとは何か?

まず、情報セキュリティが具体的に何を意味し、どのような脅威が存在するのか理解しましょう。
情報セキュリティの3要素(機密性、完全性、可用性)
情報セキュリティとは、以下の3要素を確保することと定義されています。
機密性:特定の権限を持つ人々だけが情報にアクセスできる状態
機密性とは、特定の情報が許可された人だけにアクセスできるよう保護されていることを指します。
言い換えれば、関係ない人や悪意のある人がその情報を見たり使ったりすることができないようにするということです。
日常生活での例としては、家の鍵をかけることが挙げられます。
鍵をかけることで、許可されていない人々が家の中に入ることできません。
このように、機密性は特定の情報に対して鍵をかけることと考えることができます。
完全性:情報が正確で変更されていない状態
完全性とは、情報が正確で変更されていない状態を保つことを意味します。
情報が途中で改ざんされたり、誤って変更されたりすることなく、正確に保管・伝達されることが求められます。
例えば、友達に手紙を書いて送るとき、その手紙が途中で誰かに開けられて中身が書き換えられることなどは、あってはなりません。
封筒にしっかりとテープを貼るなどして、途中で誰にも触れられず友達に正確に届くよう工夫します。
このように、完全性は情報に対して封筒をしっかりと閉じることと考えることができます。
可用性:必要なときに情報にアクセスできる状態
可用性とは、必要な時に情報にアクセスできる状態を保つことを指します。
身近な例として、水道の蛇口をイメージしてください。
手洗いや料理などで、蛇口をひねればいつでも使える水道があるからこそ、快適な生活が送れます。
しかし、何らかの理由で水道の水が止まってしまった場合、不便な日常生活を過ごさなければなりません。
同じように、可用性は情報の蛇口をひねればいつでも使える水道のようなものだと考えることができます。
情報セキュリティにおける3つの脅威(人的脅威・技術的脅威・物理的脅威)
情報セキュリティでは、情報資産(企業や組織などで保有している情報全般)に対して悪影響を及ぼす要因を脅威と呼びます。
情報セキュリティにおける脅威は以下の3つに分類されます。
人的脅威:人による誤操作、不注意、故意の攻撃など
人的脅威とは、人による誤操作、不注意、故意の攻撃などによって引き起こされることを指します。
人的脅威には意図的な脅威と偶発的な脅威の2つに分けられます。
- 意図的な脅威
故意に企業や組織の情報を損なおうとする脅威です。
情報の不正な持ち出しや情報の盗み見などが該当します。 - 偶発的な脅威
従業員のセキュリティ意識が低いことなどにより、意図せずに情報が漏れてしまう脅威です。
メールの誤送信やUSBメモリーの紛失などが挙げられます。
技術的脅威:サイバー攻撃など
技術的脅威とは、サイバー攻撃など技術的な手段によって引き起こされる脅威を指します。
セキュリティの隙間を突くことで情報を盗んだり、システムを破壊したりします。
例えば、知らないメールの添付ファイルを開いてしまったり、怪しいウェブサイトを訪れたりすると、ウイルスがパソコンに侵入する脅威あります。
このウイルスによって、個人情報が盗まれることもあれば、コンピュータが正常に動かなくなることもあるのです。
このように、技術的脅威はコンピュータやインターネットの使用において潜んでいることから、
- セキュリティソフトの利用
- ソフトウェアの定期的なアップデート
- 怪しいメールやリンクを開かないようにする
などの対策によって、重要な情報資産を守る必要があります。
物理的脅威:設備の故障や自然災害など
物理的脅威とは、物理的な要素によって引き起こされる脅威のことを指します。
例えば、自然災害や設備の故障などによって、重要なデータが失われたり業務が停止したりする恐れがあります。
【介護事業所向け】情報セキュリティ対策の具体例
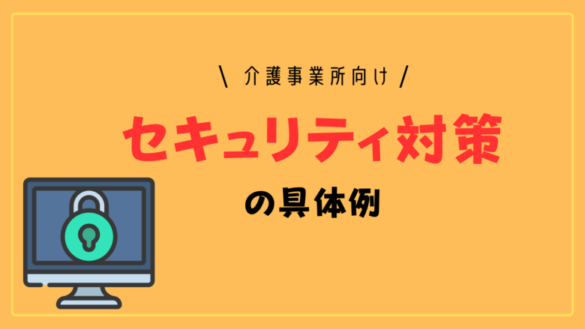
ここまでの内容(情報セキュリティの3要素、情報セキュリティにおける3つの脅威)を踏まえたうえで、介護事業所向けの情報セキュリティ対策の具体例について解説します。
セキュリティ教育の実施
セキュリティの教育は、介護事業所での情報セキュリティ対策の基盤となる部分です。
管理者及びスタッフが日々の業務中に遭遇する可能性のあるセキュリティリスクを理解し、適切に対処できる能力を育成するために不可欠です。

でも、介護事業所がセキュリティについて学べる場は少ないですよね…。

NPO法人タダカヨの勉強会に参加すれば、ICTツールやセキュリティについても学べますよ。
NPO法人タダカヨは「ITを上手に使って、お金をかけずにより良い介護へ」というビジョンを掲げ活動している非営利団体です。
タダカヨでは非営利活動の一環として、無料オンラインPCスクール「タダスク」をほぼ毎日開催しています。

情報セキュリティについての勉強会も定期的に開催されていますので、タダカヨのホームページを確認のうえ、お申し込みください。

私もタダカヨ講師メンバーとして、勉強会(タダスク)を開催しています。
お気軽にご参加ください!
BCP(事業継続計画)の策定
地震や火災などの災害によってシステムが使えなくなった場合、可用性(必要なときに情報にアクセスできる状態)が確保されていないといえます。
災害等の不測の事態が発生した場合も、重要な業務を中断させず、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させる必要があります。
そのための方針、体制、手順等を示した計画をBCP(事業継続計画)と呼びます。
災害等の発生時に事態が後手に回らないよう、BCPにおいて可用性を高める対策を示しておくべきです。
対策としては、
- データのバックアップ
- 適切な設備のメンテナンス
- 緊急連絡体制の確立
などがあります。
居宅介護支援事業所BCPの作成例は以下の記事をご覧ください。
クラウドサービスの活用
紙で保存された書類は、災害(火災、水害、地震など)によって、破損したり消失するリスクがあります。
これは情報セキュリティにおける物理的脅威となります。
その対策として、データをクラウドに保存することで、設備の一部が損傷しても他の場所からデータを取り出して迅速に復旧できます。

「クラウド」とは何ですか?
クラウドとは、インターネットを通じてデータやソフトウェアを外部のサーバーで管理する技術です。自分のパソコンや携帯に保存する代わりに、安全な場所でデータを保管し、異なるデバイスや場所からでもアクセスできます。

クラウドサービスの一つである「Dropbox」についての解説はこちらの記事をご覧ください。
クラウドサービスの活用により、物理的脅威から情報資産を保護し、業務の継続性を確保できます。
パスワード設定と管理
パスワードは、個人情報や重要なデータへのアクセスを制限するための最初の防御ラインとなります。適切なパスワード管理がないと、機密性の低下やデータ侵害などのリスクが高まります。
セキュリティ強化のための具体的なパスワード設定と管理の対策は以下のとおりです。
- 強固なパスワードの使用
十分な長さ(例えば8文字以上)を持ち、大文字・小文字、数字、特殊文字などの組み合わせが理想的です。 - 異なるサービスでのパスワードの使い回しを避ける:
一つのサービスでの侵害が他のサービスへの侵害につながらないように、サービスごとに異なるパスワードを使用することが重要です。 - 定期的なパスワード変更:
古いパスワードが漏洩するリスクを減らすために、定期的にパスワードを変更することを推奨します。 - 二要素認証とワンタイムパスワードの導入
パスワードに加えて、携帯電話の認証コードなどの二要素認証やワンタイムパスワード(一回限りの使用が可能なパスワード)を導入すると、セキュリティが一層強化されます。 - パスワード管理ツールの利用
複数の強固なパスワードを覚えるのが困難な場合、信頼性の高いパスワード管理ツールを使用することで、安全にパスワードを管理できます。
例として、Googleパスワードマネージャーは、パスワードの安全な保存と管理を提供し、異なるデバイス間でのパスワードの同期も容易にします。
モバイル機器の管理
ケアマネや訪問介護、訪問看護などの外回りが多い介護事業所にとって、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器の活用は不可欠です。
これらの機器には、利用者に関する重要なデータも保存されることがあるため、次のような安全なモバイル機器の管理が求められます。
- デバイスのロック
パスコード、指紋認証、顔認証など、モバイル機器のロックを適切に設定し、不正アクセスを防ぎます。 - 遠隔操作の設定
モバイル機器を紛失した場合、遠隔でのデータを消去やロックできる機能を有効にしましょう。 - 専用アプリの使用制限
介護事業所で使用するモバイル機器には、必要な専用アプリのみをインストールし、使用許可するように管理します。 - 定期的なセキュリティチェック
モバイル機器のセキュリティ状況を定期的に監査するとともに、修正プログラムが提供されたら速やかに適用できるよう、自動更新する設定を有効にしましょう。 - BYODの管理
従業員の個人所有のデバイスを業務に使用(BYOD)する場合、セキュリティポリシーとガイドラインを策定し、BYODの取り扱いについてのルールを確立しましょう。
※医療機関等(※介護事業者を含む)におけるBYODの対策については「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」をご参照ください。
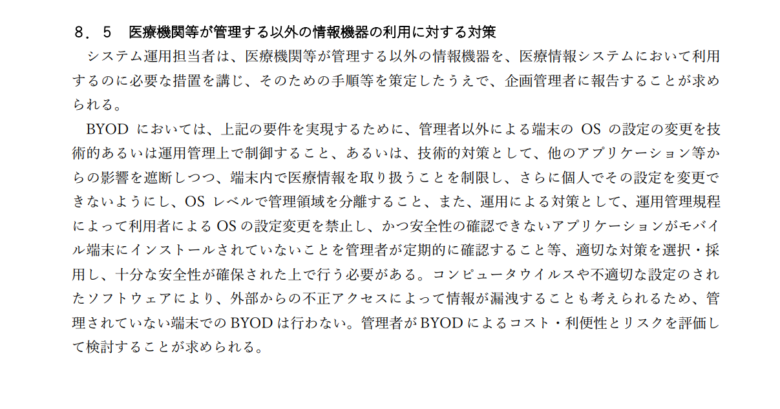
まとめ:情報セキュリティ対策を実践して安全にICTツールを活用しよう
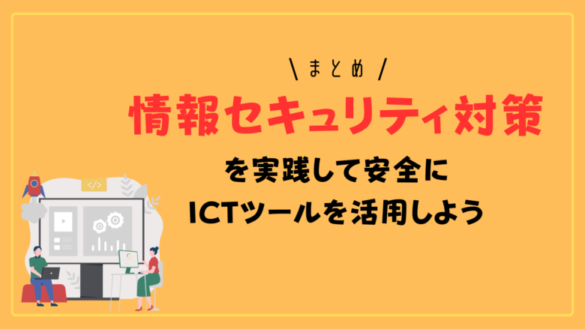
今回の記事では、情報セキュリティの基礎知識と介護事業所向けの具体策について解説しました。
情報セキュリティの3要素
情報セキュリティは、機密性、完全性、可用性の三つの要素から成り立っています。
これらは情報を適切に保護し、管理する基本となります。
情報セキュリティの3つの脅威
情報セキュリティは情報資産に悪影響を与える要因を脅威と呼びます。
脅威には、人的脅威、技術的脅威、物理的脅威の3つに分類されます。
情報資産の重要度や脅威の発生頻度などによって、適切な対応を検討する必要があります。
情報セキュリティの3要素や3つの脅威を踏まえ、介護事業所として以下の具体策を講じましょう。
多職種連携の強化や業務効率化を促進するうえでICTツールの活用は欠かせません。
介護事業所が情報セキュリティをしっかりと理解し、適切な対策を講じることで、利用者の情報を安全に保護しながら、ICTツールを効果的に活用する道が開かれます。

今回の記事が介護事業所の皆さんの安全なICT活用につながれば何よりです。
当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。









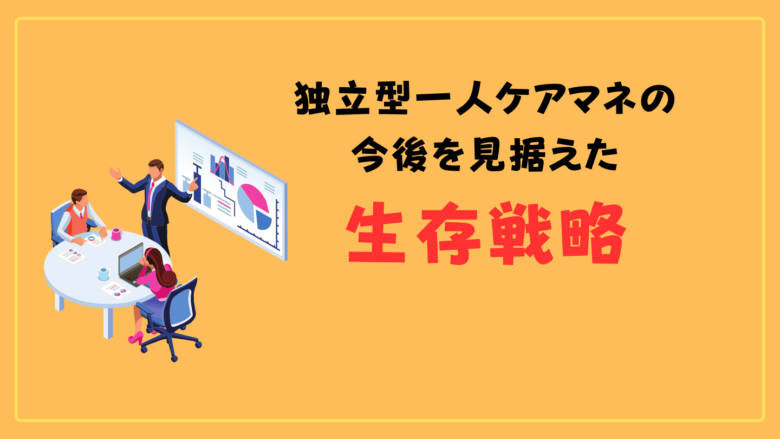
コメント